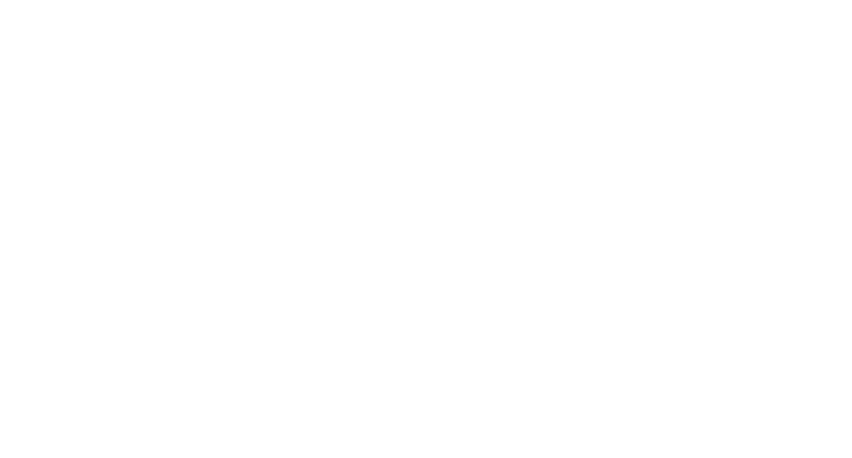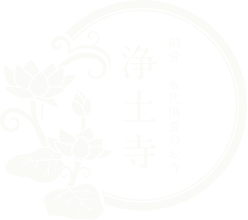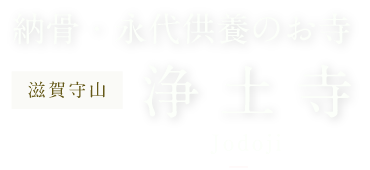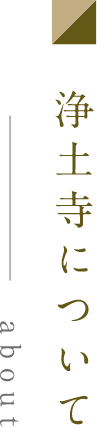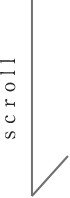-戦国の世から続く念仏供養を-
|ご挨拶|
浄土寺第三十二世住職

〜今の時代に必要とされるお寺となるために〜
令和となり、ますますお墓のことで
お悩みの声をよく聞くようになりました。
現在お墓をもたれている方であったとしても、
「子供がいない」「子供が女の子だけ」
「息子はいるけど、もう地元には帰ってこない」
などなど・・・、悩みは尽きません。
加えて、昨今「子供に負担をかけたくない」と考える
親御さんが
特に多くなったように感じます。
しかしながら、一方では
「お墓では亡くなった人に会える気がする」
「先祖が自分を見守ってくれている気がする」
「お寺に行くとなぜか落ち着く気がする」
といった声もよく聞きます。
日本ではお墓参りが伝統行事として定着し、
なおかつ、残された者にとって
お墓が大切な存在であることは揺るぎのない事実なのです。
皆様の悩みや、心の思いに応えるために、
お墓の新しい形として
「樹木葬墓地」「永代供養墓地」を作りました。
次世代の皆様に負担をかけずに
心配なく時代に寄り添った供養ができますと幸いです。
「有為転変は世の習い」といいますが、
時代が変われば仏事も変わるものです。
変化を惜しまず、
現代にふさわしいお寺づくりを行ってまいります。

永代供養で浄土寺が選ばれる理由reason for choosing
- 01駅近でアクセスが抜群JR守山駅(新快速停車駅)より徒歩7分の好立地
- 02宗旨、宗派問わず住職の作法は浄土宗
- 03年会費等の維持費なし護持費の一括払いにより、全ておまかせ
浄土寺概要overview
| 山号 | 清泰山せいたいざん |
|---|---|
| 院号 | 浄大律院じょうだいりついん |
| 寺号 | 浄土寺じょうどじ |
| 宗派 | 浄土宗じょうどしゅう |
| 宗祖 | 法然上人ほうねんしょうにん |
| 総本山 | 京都知恩院きょうとちおんいん |
| 開山 | 明応元年(1492年)めいおうがんねん |
| 本堂建立 | 永正五年(1508年)えいしょうごねん |
| 本堂再建 | 安政六年(1859年)あんせいろくねん |
| 本尊 |
阿弥陀如来坐像あみだにょらいざぞう 伝 快慶作かいけいさく |
| 寺宝 |
毘沙門天立像びしゃもんてんりつぞう 伝 運慶作うんけいさく |